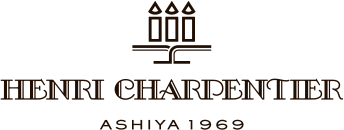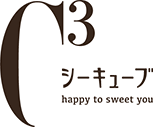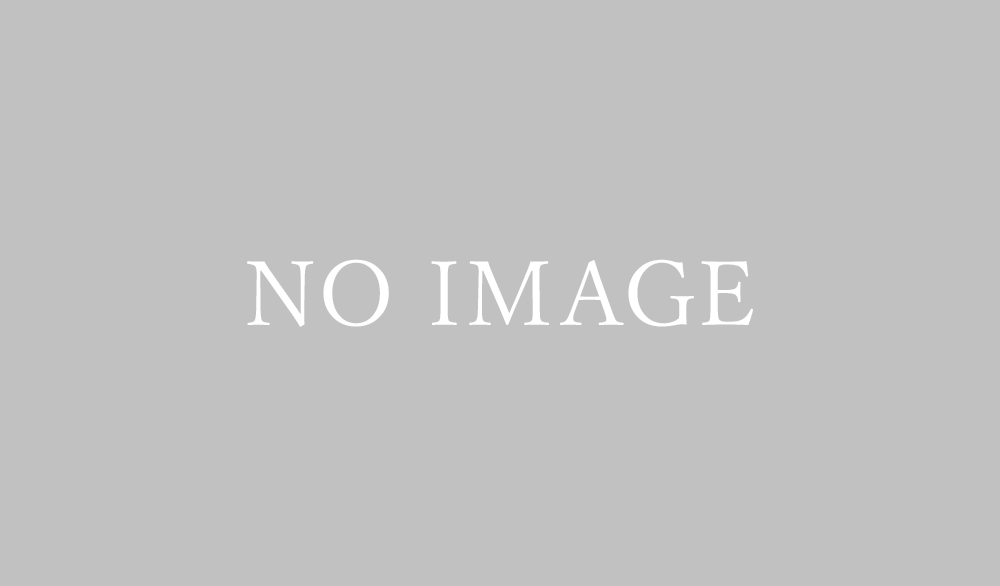お歳暮は、一年間お世話になった方々へ感謝の気持ちを込めて年末に贈る、日本の伝統的な贈りものです。しかし、お歳暮を贈る適切なタイミングについては迷われる方も多いのではないでしょうか。
一般的に、お歳暮を送る時期は12月上旬から25日頃までとされていますが、地域によっても異なります。また、年末は多忙になりがちで、準備が遅れてしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、地域ごとのお歳暮の適切な時期と便利な準備リストをご紹介します。余裕を持って準備を進めたい方に役立つ情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください。
目次
お歳暮の時期はいつからいつまで?基本のタイミングを確認
お歳暮を贈る時期は、一般的には12月上旬から12月25日頃までとされています。年末に近づくにつれてお正月の準備が忙しくなるため、遅くとも12月25日までに贈れば相手に負担がかかりにくいと考えられているからです。
ただし、地域や慣習によっては、お歳暮を贈るタイミングが異なる場合もあります。たとえば、「すす払い」としてお正月の準備が始まる12月13日に合わせてお歳暮を贈るのが適している地域もあります。相手の住む地域の習慣を確認し、負担にならないタイミングで贈るよう心がけるとよいでしょう。
地域ごとのお歳暮の時期
ここからは関東地方や沖縄地方など、地域別にお歳暮の最適な時期をご紹介します。
贈る相手が住む地域の慣習を知り、適切な時期に贈りものを届けましょう。
関東地方|12月1日から20日頃
関東地方では、お歳暮を贈る時期が他の地域よりも早く、12月1日から20日頃とされています。また、最近では企業などで早めに準備をするケースも増えており、11月下旬から贈り始めても失礼にはあたりません。お歳暮の時期が年々早まってきている傾向もあるため、関東地方の方に贈る際は早めの手配が無難です。
沖縄|12月1日から25日頃
沖縄では、お歳暮を贈る期間が比較的長く、12月1日から25日頃までとされています。受け取りに余裕を持つ方が多い地域で、旧暦の正月を祝う風習があるため、年明け後でも「お歳暮」ののしを使って贈ることがあります。
北海道・東北・関西・九州 他|12月10日から20日頃
北海道や東北、関西、九州地方など、関東や沖縄以外の地域では、一般的に12月10日から20日頃が適期とされています。ただし、年末の忙しさを考慮して、全国的にお歳暮を少し早めに贈る傾向が強まっています。贈る相手の都合を確認しつつ、少し早めに手配することで、相手も余裕を持って受け取れるでしょう。
お歳暮の準備を始める時期は?
お歳暮をスムーズに贈るためには、早めの準備と計画が欠かせません。早めに贈り先リストをまとめて贈りものを選ぶことで、年末の慌ただしい時期でも余裕を持って対応できます。
ここからは、お歳暮を早めに準備するメリットと、準備に役立つリストをご紹介します。
早めに準備するメリット
お歳暮を早めに準備することには、様々なメリットがあります。
たとえば、年末が近づくほど配送の混雑が予想されますが、11月の早い段階で準備を進めておけば、希望の時期に余裕を持って贈ることが可能です。また、贈りものの選定に時間をかけられるため、相手に喜ばれる商品を見つけやすくなります。
さらに、11月中にはショップによって「早割」キャンペーンが実施されていることがあり、これらの割引を活用することで、コスト面でもお得に準備を進められます。
アンリ・シャルパンティエの商品もお歳暮ギフトにおすすめですので、公式通販のページをぜひご覧ください。
>>お歳暮ギフト特集アンリ・シャルパンティエ公式通販
準備リスト
お歳暮の準備リストは、以下のとおりです。
| 項目 | 時期 | 詳細 |
|---|---|---|
| 贈り先リストの作成 | 10月中旬〜11月初旬 | 贈る相手の名前、住所、連絡先リストを作成します。 |
| 予算の設定 | 10月中旬〜11月初旬 | 関係性に応じて、3,000〜5,000円程度で予算を設定します。 |
| ギフトの選定 | 11月初旬〜中旬 | 相手の好みやニーズを考慮し、日持ちする食品や実用品からギフトを選びます。 |
| 発送・配達の手配 | 11月~12月 | 品物が決まり次第、発送・配達を手配します。お歳暮の申し込みから実際に贈り先に商品が届くまでには、一定の日数がかかることを考慮しましょう。 |
お歳暮の時期が過ぎた場合の対処法
お歳暮を贈る適切な時期が過ぎてしまった場合、どのように対処すべきか迷う方も多いでしょう。
基本的には、年内の12月31日までに届けば「お歳暮」として贈ることに問題はありませんが、相手に届くのが年を越してしまう場合は「お歳暮」として贈ることは避けるべきです。
しかし、感謝の気持ちは別の方法で伝えられます。年明けに「御年賀」や「寒中御見舞」として贈ることで、失礼なく感謝の気持ちを届けられます。
そこで、ここからは「御年賀」や「寒中御見舞」として贈る際の対処法をご紹介します。
御年賀として贈る
お歳暮の時期を過ぎて年が明けた場合、1月1日から7日(関西では15日)までの松の内の期間であれば、「御年賀」として贈ることができます。表書きに「御年賀」と記載すると、新年の挨拶も兼ねられ、相手にも喜ばれるでしょう。
ただし、松の内の期間を過ぎるとお年賀として贈ることはできないため、寒中見舞いとして贈りましょう。
寒中御見舞として贈る
松の内が過ぎ、立春(2月4日)までの期間であれば、「寒中御見舞」として贈ることができます。
表書きには「寒中御見舞」または「寒中御伺」と記載します。目上の方に贈る場合は、「寒中御伺」とするほうがより丁寧で尊敬の気持ちが伝わりやすく、好印象を与えられるでしょう。
また、贈り先が喪中の場合は、松の内(1月1日~1月7日)の期間を避けて、1月8日以降に「寒中御見舞」として贈ります。
喪中の際のお歳暮に関する詳細は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:喪中にお歳暮を贈っても大丈夫?マナーとギフトを選ぶポイントを解説
まとめ|お歳暮を贈る時期に合わせて早めに準備を始めましょう
お歳暮は一年の感謝を伝える日本の大切な文化です。相手に喜んでもらえるよう、早めの準備を心がけ、スムーズに贈答の手配を進めましょう。
もし準備が間に合わず、若干時期が遅れてしまった場合でも、「御年賀」や「寒中御見舞」として贈ることで、失礼なく感謝の気持ちを伝えることができます。
お歳暮ギフトに悩まれている方は、お歳暮ギフトとして人気の高いアンリ・シャルパンティエの商品を、ぜひ検討してみてください。