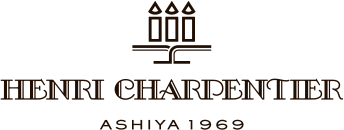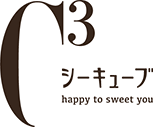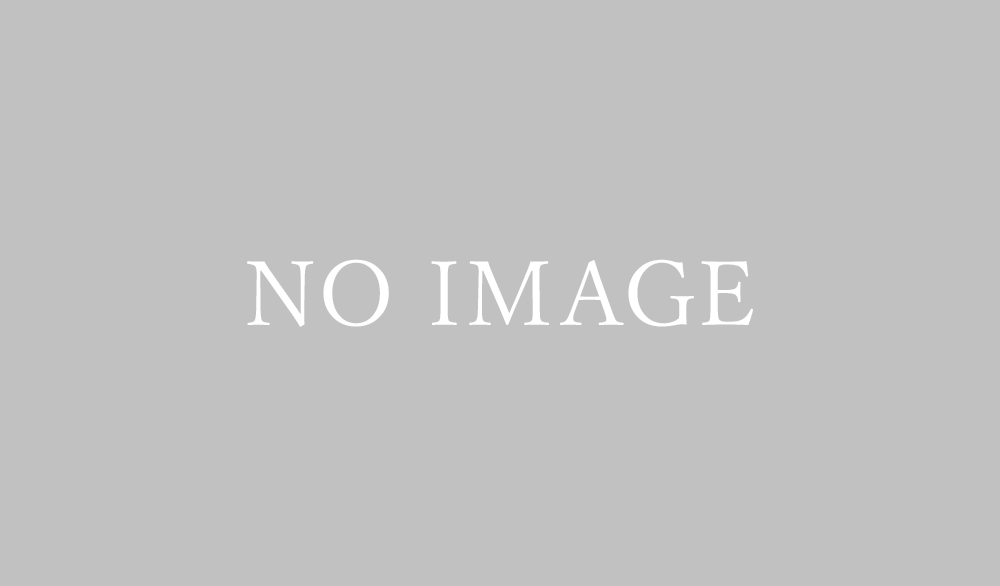日頃お世話になっている方々への感謝を込めて年末に贈られる「お歳暮」。この季節の風物詩ともいえるお歳暮をいただいた際には、感謝の気持ちを伝える「お礼状」を送ることが、最も丁寧な対応だとされています。
しかし、お礼状の書き方を誤ってしまうと、せっかくの感謝の気持ちが十分に伝わらず、失礼にあたることもあります。
本記事では、お歳暮のお礼状を正しく書くための基本構成とマナーについて詳しく解説します。お歳暮のお礼状を書く際に、ぜひ参考にしてください。
目次
お歳暮のお礼状の基本マナー
まずは、お歳暮のお礼状の基本マナーを紹介します。
お礼状のマナーをしっかり押さえ、相手に失礼のない対応を心がけましょう。
お礼状を送るタイミング
お礼状は、お歳暮が届いてからできるだけ早く送ることが大切です。一般的には、お歳暮を受け取ってから3日以内にお礼状を送るのが理想とされています。もし3日を過ぎてしまった場合には、お詫びの言葉を添えることで、失礼のない対応ができます。
また、年賀状の時期が近い場合でも、年賀状にお歳暮のお礼を添えるのはマナー違反とされています。お礼状は、年賀状とは別に送るようにしましょう。
基本は縦書きの封書
お礼状は、縦書きの封書が最も丁寧な形式とされています。そのため、目上の方やビジネスシーンで送る際には、縦書きの封書で書くことが基本です。ただし、親しい関係性の相手であれば、横書きやはがき、メールで送っても問題ありません。
手書きで感謝を伝えるときの注意点
お礼状を手書きで書く際は、以下のとおり、いくつかの注意点があります。
- 相手の名前や部署・役職などを書き間違えないようにする
- 相手との関係性で文面を変える
- 句読点を使わない
送る相手の名前や部署・役職を間違えることは大変失礼にあたります。手書きで書く際には、特に書き間違えないよう注意しましょう。
また、お礼状を書く際には、相手との関係性に応じて文面を調整することも大切です。ビジネスシーンや目上の方へのお礼状と、親しい方へのお礼状では、文面の表現を変えていくとよいでしょう。親しい相手に対しては、堅苦しすぎる文面よりも、素直に感謝の気持ちが伝わる内容にするほうが好まれます。
さらに、お礼状を書く際には句読点を避け、改行や空白で文章を区切ることが望ましいとされています。句読点は、もともと子どもが文章を読みやすくするために使われ始めた経緯があり、お礼状で使用すると相手を子ども扱いしていると受け取られることがあります。また、句読点は「縁を切る」という意味合いにとらえられることもあるため、注意が必要です。
お礼状の基本の構成
お歳暮のお礼状を作成する際には、基本的な構成を押さえることで、感謝の気持ちを相手にわかりやすく伝えられます。
一般的なお礼状の構成は、以下のとおりです。
- 頭語
- 時候の挨拶
- お礼の言葉
- 相手の健康や幸せを願う言葉
- 結語(敬具・謹白など)
- 日付と署名
<頭語>
手紙の冒頭に相手への敬意を表す言葉で、ビジネスシーンでは「拝啓」や「拝呈」の使用が一般的です。手紙の締めくくりに使う結語とはセットで使用します。
<時候の挨拶>
季節を表現する挨拶です。相手との関係性によっても、時候の挨拶の表現は変わります。時候の挨拶のあとには、「いかがお過ごしでしょうか?」のような相手の安否を気遣う内容を入れると、文章がより丁寧な印象になります。
<お礼の言葉>
頂いたお歳暮へのお礼の言葉です。相手との関係性によっては、家族も喜んでいることを伝えると、より感謝の気持ちが伝わるためおすすめです。
<相手の健康や幸せを願う言葉>
寒さが増す年末の季節にふさわしい、相手の健康を気遣う言葉を添えます。「どうぞご自愛ください」など、相手を思いやる気持ちを伝えるとよいでしょう。
<結語>
「敬具」や「謹白」など、頭語と対になる結語で締めくくります。
頭語と結語の組み合わせ
お礼状を書く際には、頭語と結語の適切な組み合わせを確認しておきましょう。
以下に、よく用いられる頭語と結語の組み合わせを表形式で示します。参考にしてください。
| 頭語 | 結語 |
|---|---|
| 拝啓 | 敬具 |
| 拝呈 | 敬白 |
| 啓上 | 拝具 |
| 謹啓 | 謹言 |
| 謹呈 | 謹白 |
一般的な手紙では頭語に「拝啓・拝呈・啓上」が多く用いられますが、目上の方や客先などより丁寧な表現にしたい場合は「謹啓」「謹呈」を使用します。頭語と結語は、送る関係性に合ったものを使用することが大切です。
時候の挨拶
お歳暮のお礼状では、季節感を大切にした時候の挨拶を添えると、相手に温かみが伝わります。
以下に、ビジネス向けと個人向けで適した時候の挨拶をいくつかご紹介します。
<ビジネス向け>
- 「歳末の候 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます」
- 「寒冷の候 貴社ますますご隆盛のことと拝察いたします」
- 「寒冷の候 貴社ますますご隆盛のことと拝察いたします」
<個人向け>
- 「師走に入り寒さも本格的になりましたが 風邪などひかれておられませんか」
- 「師走を迎え、何かと慌ただしい時期ですが 皆様お元気にお過ごしでしょうか」
- 「日ごとに寒さが増してまいりましたが お変わりございませんでしょうか」
相手との関係性に応じて適切な表現を選び、季節にふさわしい時候の挨拶を添えていきましょう。
お歳暮のお礼状に適した文例集
お歳暮のお礼状を作成する際には、相手との関係性やシチュエーションに応じた文例を選ぶことが大切です。
以下に、ビジネスシーンや個人宛てに適した文例をいくつかご紹介します。
お礼状には本来句読点を使わないため、封書やはがきで送る際の文例では句読点を省いていますが、メールの場合は略式となるため、句読点を使用した文例を提示しています。
<ビジネスシーン向けのお礼状文例>
ビジネスにおいては、会社間や上司へのお礼状では礼儀を重んじた表現が求められます。また、縦書きの封書を使用するのがおすすめです。
ビジネス向け文例1:封書やはがきの場合
| 拝啓
歳末の候 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 敬具 令和〇〇年〇月〇日 |
ビジネス向け文例 2:封書やはがきの場合
| 拝啓
師走の候 貴社におかれましてはいっそうご隆盛のこととお喜び申し上げます 敬具 令和〇〇年〇月〇日 |
ビジネス向け文例 3:メールの場合(略式のため、句読点を使用しています)
| 件名:お歳暮の御礼
株式会社〇〇 拝啓 師走の候、貴社にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 敬具 会社名 |
<個人宛てのお礼状文例>
親しい方や親族など個人宛のお礼状では、あまり堅苦しくなりすぎず、少し柔らかい表現で書くのがおすすめです。
個人宛てのお礼状文例1:封書やはがきの場合
| 拝啓
師走に入り寒さも本格的になりましたが 風邪などひかれておられませんか 敬具 氏名 |
個人宛てのお礼状文例2:封書やはがきの場合
| 拝啓
日ごとに寒さが増してまいりましたが 皆様いかがお過ごしでしょうか 敬具 氏名 |
個人宛てのお礼状文例3:メールの場合(略式のため、句読点を使用しています)
| 件名:お歳暮ありがとうございました
〇〇様 いつもお心にかけていただき、ありがとうございます。 このたびは素敵なお歳暮の品をお送りいただき、心より御礼申し上げます。家族一同、大変喜んでおります。 年の瀬も近づき、何かとお忙しい頃かと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。来年もお会いできることを楽しみにしております。 取り急ぎ、お礼まで申し上げます。 名前 |
お歳暮のお礼状でよくある質問
お歳暮のお礼状を作成する際には、マナーや対応についてさまざまな疑問が浮かぶことがあります。
ここからは、お歳暮のお礼状でよくある質問について解説していきます。
お歳暮のお礼状でタブーとされることは?
お歳暮のお礼状には守るべきマナーが多くありますが、特に避けるべきタブーとしては、年賀状とお礼状を兼ねることです。
年賀状は新年の挨拶に専念するものであるため、年賀状にお歳暮のお礼を書き添えるのは失礼にあたります。また、句読点の使用も避けるべきとされています。
お礼状と一緒にお返しをしたほうがよい?
お歳暮をいただいた場合、基本的にはお礼状のみで感謝を伝え、お返しをする必要はありません。お返しを用意することでお礼状の到着が遅れることは避けるべきです。
どうしてもお返しを贈りたい場合は、お礼状と時期をずらし、御年賀や寒中見舞いとして、いただいた品物の半額程度の品物を贈るとよいでしょう。
代筆でお礼状を送る場合の注意点
お歳暮のお礼状は、本来、感謝の気持ちを直接伝えるために自筆で書くのが望ましいものの、状況によっては他の人が代筆する場合もあります。
ビジネスシーンや家庭内で代筆が必要な際には、マナーを守り、相手に失礼のないような配慮が大切です。
家族内で代筆が必要な場合は、手紙の差出人欄に「内」と記載するのが礼儀とされています。この「内」は、家族を代表してお礼状を出していることを示すためのものです。
夫の代わりに妻が代筆する場合、縦書きの封書では夫の名前の左下、横書きでは右下に「内」を記載するのが一般的です。
書き方例
| 令和〇年〇月〇日 (夫の氏名) 内 |
ただし、「内」は相手が妻の名前を知らない場合に使用されるため、親戚などで妻とも面識がある場合には、連名にするとよいでしょう。
ビジネスシーンでは、上司や先輩が忙しく代筆を依頼されるケースもあります。その際は、差出人の役職と名前のあとに「代」と代筆者の苗字を記載するのがマナーです。代筆者が明示されることで、相手に対して失礼のない対応ができます。
書き方例
| 営業部長 山田太郎 代 鈴木 |
お歳暮を辞退したい場合の対応は?
お歳暮を辞退したい場合は、次回からのお歳暮をお断りすることが一般的です。理由を添え、相手の厚意に対する感謝の気持ちをしっかりと伝えてください。辞退の意思を伝える方法としては、お礼状や電話が適しています。
感謝の気持ちを述べたうえで、「日頃から十分なお心遣いをいただいておりますので、今後はお気軽にお考えいただけるとありがたいです」といった柔らかな表現で辞退の意思を示すと、相手に失礼がありません。さらに「今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます」といった文言を添えることで、より角が立ちにくくなります。
また、会社の規定で辞退が必要な場合は、「社内規定により贈答品をお受け取りできないこととなっております」と簡潔に伝え、相手に理解を求めましょう。
まとめ|お歳暮のお礼状のマナーを守り、感謝の気持ちを伝えましょう
お歳暮のお礼状は、贈り主に対して感謝の気持ちをしっかりと伝える大切な役割を持っています。
マナーに沿ったお礼状を送ることで、相手への敬意や配慮が伝わり、今後の関係もよりよいものとなるでしょう。本記事で紹介したマナーや注意点を参考に、お礼状で感謝の気持ちを伝えてください。